第12回市民協働推進シンポジウム「大切な人を亡くして、生きていくということ~グリーフケアでつながるまちへ~」開催しました!!
いつか誰もが経験するかもしれない、大きな悲しみ……。大切な人との死別は、心や体にさまざまな変化をもたらします。グリーフケアとは、そんな悲しみの中にある人に寄り添い、サポートすること。
心に穴が空いたとき、人と人とのつながりの中で、自分自身をケアする力を育てることができます。そんな仕組みがあちこちにある豊かなまちを目指して、少しずつ、でも着実に今、グリーフケアの輪は広がっています。
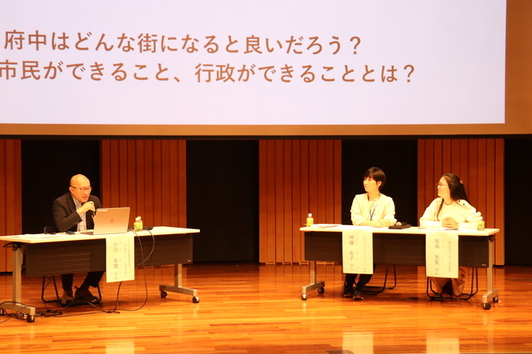
<第一部:尾角光美さん講演「なくしたものと、つながる生き方」>
「2003年3月、私が19歳のとき、母は自殺で亡くなりました。母と一緒に、私も母の死を選択した感じがします」
尾角さんの穏やかな表情と声でシンポジウムは始まりました。
「私が今、ここにこうしているまでに、世の中からたくさんの恩を受けました。その恩を今苦しんでいる人へ送りたい、恩送りをしたいです。
私たちは必ずいつか大切な人を失います。そのとき手を伸ばした先に、その手を取ってくれる人や組織や行政がある、そんな社会を目指しています」

「グリーフとは、喪失への反応のこと。大切な人・ものなどを失うことによって生じる、その人なりの自然な反応や感情、プロセスのことです。その中には「安心」する気持ちも含まれることがあります。私も母を亡くしたあと、母がやっと苦しみから解放されたのだとほっとしました。どの感情も大事に、抱きしめてください。
…いつになったら乗り越えられるの? …時が解決するんでしょう? …こんなふうに言われることもあるかもしれません。でも、「時薬」は万能薬ではありません。
亡くなった人のことを想い、失ったことについて考え、回復を否定する。これを喪失志向といいます。また、新しい役割や生活に適応し、自分の将来に向かって生きる。これらを回復志向といいます。
喪失志向から回復志向へ向かうことがよいのでしょうか? いいえ、そうではなく、このあいだを「ゆらぐ」ことが大切なのです。ゆらいでいい。死や喪失を「乗り越える」のではなく、なくしたものとつながりなおす、そのためのいとなみがグリーフワークなのです」
また、まわりに喪失感を抱えて苦しんでいる人がいるとき、どのように接すればいいのかについても尾角さんは話してくださいました。
「グリーフは指紋と同じくらい、人それぞれ違うのだといわれます。
私たち一人ひとりにできることは「大切に聴く」ということ。聴くことには力があります。「眠れている?」「何か食べられた?」など、積極的関心を持つその眼差しがグリーフケアなのです。そして対話をするときには、ジャッジをわきに置き相手の感じ方をそのままに尊重します。同じ喪失の人はひとりとしていないのです。
また、自分自身を大切にすることが、他者との関係においても重要です。自分に与えている「セルフケア」の質が、他者との間に生まれるケアにつながっていきます。今日、眠るまでに、自分にしてあげられるセルフケアはどんなことでしょうか?考えてみてください」
コロナ禍では、死別の理由がコロナだと言えない「公認されない悲嘆」があり、遺族が亡き人を語れない、悲しむことさえはじめられない状況がありました。どんな死も平等に、どの生も大事にされる社会へ。尾角さんの優しく強いメッセージとともに、第一部は終了しました。
<第二部:パネルディスカッション「グリーフケアで、つながるまちへ」>
二部のコーディネーターは、府中市内のお寺の住職である小川有閑さん。小川さんは、親しい人を喪った子どもたちや家族のための施設であるアメリカ・ダギーセンターで研修をしたこともあり、現在は小金井公園のそばで「エッグツリーハウス」を運営しています。近親者を亡くした子どもは、そのことを家や学校でなかなか言えません。エッグツリーハウスは、それを隠すことなく遊べる場所なのです。
パネラーは尾角光美さんに加え、市民団体「ふちゅうのグリーフサポート」代表の神藤有子さんが登壇しました。20代でパートナーとの別れを経験したあとも、看護師としての仕事を続けてきた神藤さん。遺族の自分と看護師の自分、ふたつの「わたし」を心に抱える中で、ひとりの人が亡くなる前も亡くなったあとも、ずっと何かのかたちで家族・遺族の支えになれないかとの思いから活動を始めたそうです。
死が個人化した現在。遺族はまちでも職場でも「普通の顔」をして過ごさなければなりません。死を地域で共有し、近隣住民が遺族を支える「古き良き昭和」の社会はもう戻らないのです。
三名の登壇者は、どんなふうに大切な人の死を受け止めたのでしょうか?
神藤さん:簡単に答えると「簡単には受け止められませんでした」ということですね。助けてとは言えない性格で、なかなか前に進めませんでした。
尾角さん:ひとりで受け止めなくてもいいんだ、ということが支えになりました。連絡する先があったので。
小川さん:母が亡くなってからお葬式までに少し日にちがあったので、その間、弔問に来てくださった方に何度も何度も母のことを話しました。積極的関心を持って聴いてくれる人に語る、そのことで支えられました。普段からグリーフケアをやっているひとたちだって、身近な人の死をすぐに受け止められません。そんなもんです。


会場からも、さまざまな質問が寄せられました。
質問「いつまで経っても悲しみから抜け出せず、グリーフワークができないのですが、どうしたらいいでしょうか」
尾角さん:グリーフワークは、自分がしたくてできるときにすることが大切。つらい、したくないのであれば距離をとっていいのです。選択肢として持ちながら生きていくということでしょうか。一年以上日常生活を送れていないのであれば、専門機関に相談しましょう。そうではなく、日常生活は送れているけれど悲しくてということならば、自分の中にある悲しみと向き合う手立てをゆっくりと探していくことからだと思います。
質問「家族を亡くした人の話をいろいろと聴いてあげて、グリーフサポートの情報も伝えました。そうしたら、話を聴いてくれたことは嬉しかったがグリーフサポートの情報は余計だったと言われました。情報や選択肢は、どうしたらうまく伝えられるでしょうか」
神藤さん:職場で悲しそうな人がいると、心配になるけれどどうしたらよいのかわからないという気持ちがめぐりますよね。気にかけているよ、というサインがうまく伝わるといいのですが。いつも通りに接してほしいという遺族もたくさんいますし。
尾角さん:情報は、渡さなければその人にとって必要か必要でないかもわかりません。情報はあまねく人々に届けることが大事です。でも選ぶのは本人です。あなたにとって必要であれば手を伸ばせばいい、選ぶのはあなたですよという感覚を忘れなければ、おしつけがましくならないのではないでしょうか。
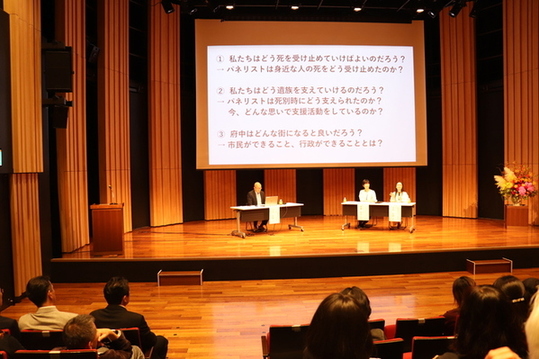
「グリーフケアでつながるまち」として、府中市はどんなまちになるとよいのでしょうか?
神藤さん:「ふちゅうのグリーフサポート」の活動を通じて、2年半で250人の遺族と会いました。遺族は大切な人を喪ったばかりで体力も気力も思考力もない、そんなぎりぎりの状態で文化センターへ行って、そこで私たちの開催している「わかちあいの会」のチラシに出会って、「奇跡だ!やっと見つけた!!」と思ったと言われたことがあります。
市役所にはおくやみコーナーができて、手続きに関する相談が一か所でできます。地域包括支援センターや、社会福祉協議会のわがまち支え合い協議会などでグリーフについて相談したという人もいます。いろいろなことに対応できる場所が、府中にはぎゅっと詰まっています。いろいろな職種の人が連携してサポートをし、そして支えるその人自身もまたサポートが受けられる。今以上にそういうまちになっていったらいいなと思います。
人生で起こる、さまざまな出来事。その中にはどうしても避けられない、つらいこともあります。グリーフケアの活動は、私たち皆にとって我が事なのです。
幸せなときも、悲しみの中にいるときも、手を伸ばせば誰かとつながることができるまち。そんなまちをつくるため、私たちにできることは何でしょうか。
尾角さん、小川さん、神藤さん、そしてバルトホールでご参加いただいた200人の皆さんとともに、じっくりと考えることができたシンポジウムでした。


