プラッツ情報紙kokoiko第26号2023.10.1
私たちの住むまちには、つらい経験をしたのちに、グリーフケアの活動に取り組み始めた人たちがいます。心に穴が空いたとき、人と人とのつながりの中で、自分自身をケアする力を育てることができる。そんな仕組みがあちこちにある、豊かなまちになることを目指して。
少しずつ、でも着実に今、グリーフケアの輪は広がっています。
亡き人への 想いとともに 生きるということ

大切な人との死別は、人生において大きなできごと。
ひとりでは抱えきれない、でも誰にも話せない。
そんな胸の内を、どうしたらいいのでしょうか。
私たちの住むまちには、つらい経験をしたのちに、グリーフケアの活動に取り組み始めた人たちがいます。心に穴が空いたとき、人と人とのつながりの中で、自分自身をケアする力を育てることができる。そんな仕組みがあちこちにある、豊かなまちになることを目指して。
少しずつ、でも着実に今、グリーフケアの輪は広がっています。
【グリーフケアとは…?】
グリーフ(悲嘆)とは、喪失体験によって起こるさまざまな反応のこと。特に大切な人と死別した時の悲しみを指します。
グリーフケアは、その悲しみに寄り添い、サポートすることをいいます。
グリーフにやさしいまちへ
グリーフに関わる活動を続ける神藤さんと小川さん。近しい人を亡くした方々との関わりの中で、お二人がそれぞれに感じていらっしゃることをお話しいただきました。

神藤有子さん
市民団体「ふちゅうのグリーフサポート」代表。家族を突然死で亡くし、その後グリーフサポートを学ぶ。参加者が自身の死別経験を話す「わかちあい」の会を開催する他、死別やペットロスについての講義なども行う。「訪問看護ステーションいきいき」看護師。

小川有閑さん
大正大学地域構想研究所・BSR推進センター主幹研究員。
子どものグリーフケアに取り組む「一般社団法人TheEgg Tree House」代表理事をつとめるなど、グリーフケアや自死対策に携わる。浄土宗・蓮宝寺住職。
―活動の背景には神藤さん自身の経験や想いがあったそうですが、 当時のことをお話しいただけますか?
神藤:看護師として病院で働いていたときから、「身近な人を亡くしたら悲しみも苦しみも全部自分で何とかしなきゃいけない。そういう社会なんだな」と思いながら仕事をしていました。死別をした人が気持ちをしゃべる場所がどこにもなければ、どこに相談したらいいのかわからない。そういうものが皆無だな、という視点はずっと持っていましたね。
私自身、28歳のときに急に家族を亡くし、ある日突然自分が遺族になりました。大切な人に急に亡くなられるというのは、心づもりも何もなく、あまりにも苦しくて。さらには「自分は大丈夫」と周囲を頼らず、頑なに我慢する生活をしていました。
そうした “死別のあとの苦しい自分”に変化をもたらすきっかけになったのは、グリーフサポートについてあらためて勉強をしたことです。学びは自分の心を癒してくれたし、やがて「グリーフサポートを通して他の誰かに関わろう」と思うようになりました。その後、プラッツを通じて実際にニーズがあることを知ったのをきっかけに、「それなら早くやろう」と。当時出会った小川さんにも色々教えていただきながら準備が整ったのを感じた頃、グリーフサポートの活動を始めることになりました。
小川: 神藤さんの活動で良いなと思うのはグリーフ“サポート”と言うところ。“ケア”というと「ケアする・される」という感じに抵抗をもつ人もいるでしょう。誰もが遺族になるので、お互いに支え合うという意味で“サポート”だと抵抗感が和らぐのかなという気がします。
グリーフケアという言葉は日本ではまだ20年くらいですけど、人類はグリーフケアをやってこなかったのかっていえば、はるか昔からやっているわけで。専門家しかできないものではなくて、家族を亡くした人がいれば、お悔やみを言ったりお世話をしたりする。そういう人間の本能、自然な営みが、グリーフケアなのではないかとも思います。
―お二人がそれぞれの活動の中で、「グリーフの手助けができている」と 感じられるのはどういったことでしょうか?

神藤:グリーフサポートの一環としてわかちあいの場をつくっていますが、そこでは大切な人を亡くした方が自分の気持ちを話すなかで体験や気持ちを分け合えたり、そして他の人との心のつながりができたりもします。参加者からの「癒された」という言葉には、「わかってもらえた」「受けとめてもらった」といった気持ちがあるのかなと感じますね。
「ここでなら話ができる」という安心感は大きいと思います。わかちあいで少し開けた心の蓋を、そこで話せたことでまたそっと閉じて、再び日常の中に戻っていく。そうやって自分の中でバランスをとっているように感じますね。
小川:子どもの場合は反応がより直接的なので、死別を経験した子どもたちは「相手にどんな反応をされるかわからない、分かってもらえないだろう」という不安から、学校では親や兄弟が亡くなったことを言わないで過ごしていたりします。
10歳前後で身近な人を亡くしているって、人生で最大の出来事ですよね。それを普段は隠しながら友達と過ごすというのは、けっこう安心して遊べていないなぁと思って。たかが月2時間のプログラムですけど、きっと子どもたちにとって「ここではみんな誰かとの死別体験があるんだ」という安心の中で遊べる貴重な時間なんだなと思っています。
―“グリーフの状態”にある人は、自身の状況をどのように捉えたらいいのでしょうか

神藤:死別によって起こる反応は人それぞれ違いますが、すべて自然なことであって「病気ではない」と伝えたい。出生の喜びも死別の苦しみも根っこは同じ、人の自然な営みです。それにまつわる症状も当たり前の反応なんです。
でも、「こんなに苦しいんだから病気かも」って思っちゃいますよね。やっぱり死別って、人生の中で一番っていうくらい苦しいですから。大好きな分だけ苦しみは比例するし、1年経っても2年経っても、むしろ時が経ってからが「本当にさみしい」という方もいます。本当の病気になってしまうケースもあります。
小川:近しい人との死別は人生で経験するストレスでいうと一番だとも言われています。死別は「自分を喪う」ようなこと。亡くなった人との関係性でできていた“私の部分”がなくなってしまうように感じることもある。元に戻ることはないので、回復したり乗り越えたりするものでもないのかなと。グリーフサポートでは「折り合いをつける」という言い方になりますね。サポートを受けながら、自分なりに折り合いのつけ方をおぼえていくということでしょうか。
―活動の今後について、思うことをお聞かせください。
小川:市民活動全般に言えることですが、始めたからには続けることが大事です。身の丈に合ったサイズで、無理をしない。それは自分のためでも参加者のためでもあるし、続けていれば課題も見えて、どこにつないだらいいのかというのも見えてきますから。そういう点でも神藤さんの活動は、順調にいっているように拝見しています。
神藤:「活動は無理しちゃいけない」というのを、小川さんから言ってもらったので。ご遺族のためにと考えるなら、長く在り続けることは必要ですよね。
そのうえで、今後は「どうしたら色んなご遺族にグリーフケア・グリーフサポートが届くか」ということも課題だと考えています。一番良いのは社会の中でこれらの敷居が下がり、死別の話や相談が自由に気軽にできるようになること。そしてさまざまな人が自分の得意分野で「グリーフサポートできる人」になってくれたらいいですね。そうしたら府中はもっと“死別のグリーフにやさしいまち”になるんじゃないかなと思います。
取材:亀谷のりこ/ 文:伊藤薫(市民ライター)
悼(いた)みの先に出会えた自分
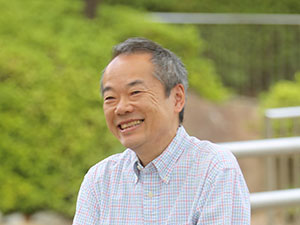
福村文生さん
パートナーとの死別をきっかけに「ふちゅうのグリーフサポート」のメンバーとして活躍されている福村文生さんにお話を聴きました。
グリーフケアへの扉
私が53歳の時、「定年後は故郷で暮らしたいね」と話していた矢先に、6歳年下の妻が病気で他界しました。手術してから5か月後、あっという間のことでした。我が家はよく妻が率先して決めたことに私が賛同することが多く、2人でいつも寄り添って暮らしてきました。こうして穏やかな日々がずっと続いていくのだろうと疑いもしなかった…。妻という拠り所を失った私は、次第に「こんな先の見えない状態で、どうやってこの人生の危機を乗り越えたらいいのか、同じ経験をしている人からも聴いてみたい、グリーフケアを学んでみたい」と思うようになり、上智大学グリーフケア研究所の講座に参加しました。
講座で学んだことの一つが「鎧を外す」ことでした。鎧と言うのは自分の心のうちを守るものの例えです。一般社会では死別の体験をあまり話したりはしませんよね。でも講座の仲間はそれをわかちあえる人ばかりだったので、「わかってもらえる」と安心して身を委ねられるようになり、鎧を外して胸の内を吐露できるようになりました。
「新しい自分」という贈り物
実は私はもともと無口で「仕事以外では人と話したくない」「人のお世話なんて面倒だな」と思う人間でした。でも安心できる仲間に出会えたことで、人の役に立ちたいと思うようになって。誰かの役に立てると、今度は「ありがとう」と喜んでくれることが嬉しくて楽しくなってきて。まさかこんな新しい自分に出会えるなんて思ってもみませんでしたよ。これは妻の命を引き換えにいただいた、大切な贈り物だな、と感じています。妻には恩返しできないけれど、同じように苦しんでいる人の力になりたいと思い、ご縁があって「ふちゅうのグリーフサポート」に参加し、「つきあかり」というわかちあいの会のお手伝いをしています。
大切な人が亡くなった時、悲しみの感じ方はそれぞれです。悲しみは時に大きくなったり、小さくなったり形を変えていきますが、決して乗り越えるものではなく、抱えていくもの。意外と人間って力があるもので、それを抱えていく力がついてくる。自分の力を信じて、これからを過ごされるのが大事ではないですかね。そして悲しみの中、孤独に苛まれている人がいたら、「あなたはひとりではないですよ」と、そっとお伝えしたいですね。
取材・文:亀谷のりこ(市民ライター)
第12回協働推進シンポジウム 「大切な人を亡くして、生きていくということ~グリーフケアで、つながるまちへ~」
大切な人との死別は、心や体にさまざまな変化をもたらします。
グリーフケアとは、そんな悲しみの中にある人に寄り添い、サポートをすること。
自分自身の辛い経験を経て支援活動をしている人たちから、私たちの住むまちで少しずつ広がっている「グリーフケアの輪」について聞いてみませんか。
※今号の特集記事で対談していただいた、小川有閑さん・神藤有子さんも登壇します!
日時 11月11日(土)14時~16時
場所:市民活動センター「プラッツ」 バルトホール
定員:先着250人
費用:無料
内容:
第一部・「なくしたものと、つながる生き方」尾角光美さん(一般社団法人リヴオン代表)
第二部・「グリーフケアで、つながるまちへ」
小 川有閑さん(大正大学地域構想研究所主幹研究員)、 神藤有子さん(ふちゅうのグリーフサポート代表)
申込:申込フォーム(https://bit.ly/3P5CZKK?r=qr)から、又は電話(042-319-9703)で受付
主催:府中市市民活動センター プラッツ/府中市
kokoiko26号アンケート&プレゼント

尾角光美著『なくしたものとつながる生き方』
kokoiko26号のご感想、今後取り上げてほしいテーマについてアンケートにお答えください。
ご回答いただいた方の中から抽選で2名様に、尾角光美著『なくしたものとつながる生き方』をプレゼントいたします。
応募方法

二次元コード、アンケートフォーム(https://bit.ly/35CQkr7)からのご応募、または官製ハガキに感想をお書き添えのうえ、下記宛先までお送りください。
〒183-0023
東京都府中市宮町1-100ル・シーニュ5階
府中市市民活動センター プラッツ kokoiko係
応募締切:2023年10月31日
※当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
kokoiko25号にお寄せいただいた「読者の声」を抜粋してご紹介します。
「車椅子のまま遊べる滑り台があることを初めて知りました。他の媒体で取り上げることの少ないテーマで、興味深く読ませていただきました。個人的に印象に残ったのは428カフェ+市川さんの、就労に問題ないスタッフ側への声掛けについてです。勉強になりました。しっかりと取材して丁寧に文章にされている感じがしました。」
【編集部より】
よりよい「共生」のためには、さまざまな立場から“伝えること・知ること”が大切なのですね。このような感想をいただけたことをとても嬉しく思います!
「あらゆる人が排除されないインクルーシブ社会の記事を興味を持って読みました。
裏面のブラインドメイクの記事が一番興味深く読むことができました。視覚障害のある方はメイクはどうするんだろう、なんとなく疑問ではありました。きれいで居たいのは誰もが思う気持ちかと思います。排除されずきれいで居られるのはとても素晴らしいと思い、インクルーシブというメインテーマにも沿っておりよかったです。」
【編集部より】
感想をお送りいただきありがとうございます。ブラインドメイクについて知っていただけて良かったです。メイクをすることで元気になることってありますよね。メイクの力ってすごいなと思います。これからも興味を持っていただける記事を提供できるよう頑張ります。
団体登録しませんか?

団体登録情報はこちらから
※詳細は市民活動ポータルサイト「プラnet」をご覧ください。
プラッツに市民活動団体登録をすると、団体活動スペースの予約利用や印刷室、各種貸出機材の活用、さらにWebやSNS等での情報発信、各種イベントへの出展など、活動を広げるチャンスがたくさんあります。
府中を拠点に、誰もが住みやすい地域や社会のために団体活動を展開している皆さまのご登録、お待ちしています。
プラnet | 府中市市民活動ポータル (fuchu-planet.jp)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明に従ってインストールしてください。


